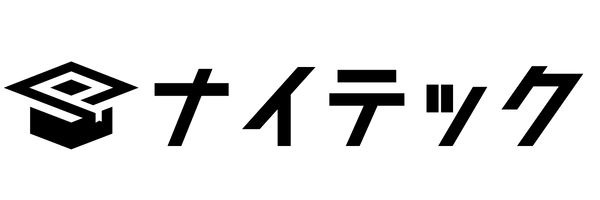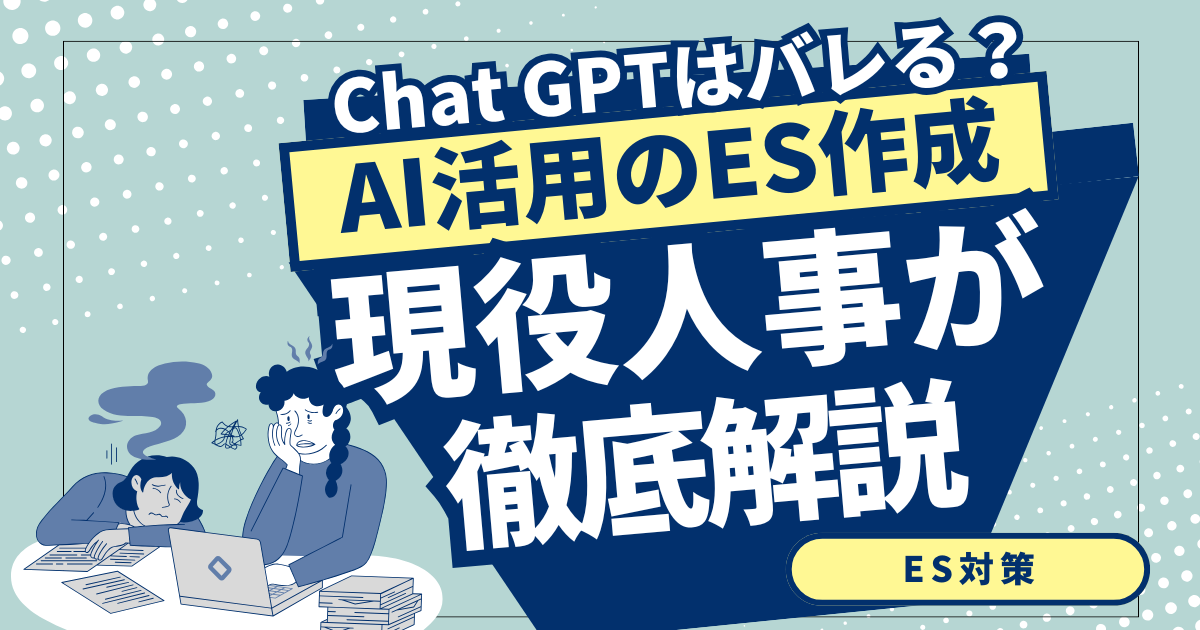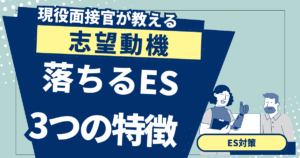はじめに
「ChatGPTでESを書いたら、人事にバレますか?」
ここ1年、採用現場で最もよく耳にする質問です。
結論から言えば——“バレることはある”が、使い方次第で“通るES”にもなる。
採用担当が問題視しているのは、AIの使用そのものではありません。
本質的な問題は、「自分の思考を経由せず、整った文章だけを提出してしまうこと」です。
AIが生成したESは、文法的には正しく、論理も整っています。
それでも評価が上がらないのは、“思考の跡”が感じられないからです。
採用担当は文章を読むとき、
「この学生は、どんな視点で考え、どう決断したのか」
を探しています。
言い換えれば、人事が見ているのは「語彙の美しさ」ではなく、**“意思の深さ”**です。
AIは嘘をつきませんが、生きた経験を語ることができない。
だからこそ、AIに任せきりのESは、正確であるほど“薄く”見えるのです。
では、AIが生成した文章のどこに人事は違和感を覚えるのか。
そして、どうすればChatGPTを使っても“人事に伝わるES”を作れるのか。
本記事では、現役の新卒採用担当として数千枚のESを審査してきた立場から、
AIで作ったESがバレる構造、評価が下がる理由、
そして**“通過率を上げるための正しい使い方”**を徹底的に解説します。
ES~面接対策まで徹底した個別指導ならナイテック
ChatGPTを使いこなす学生が、なぜ通過率を上げているのか?
答えは、“AIで整え、人間で意味づける”ことにあります。
ナイテックでは、AIの使い方だけでなく、
人事が「伝わる」と感じる言葉選びまでを徹底的に指導。
あなたのESを「整っている」から「惹きつける」へ。
👉 AI時代に通用するESを、一緒に作りませんか?
第1章|ChatGPTで書いたESは“構造でバレる”
ChatGPTで作成したESは、文章を第1章|ChatGPTで書いたESは“構造でバレる”
近年、採用現場ではAIで生成されたES(エントリーシート)が急増しています。
そして多くの人事担当者が口を揃えて言うのが、
「AIで書かれたESは、一読すればわかる。」
それは経験や勘といった曖昧なものではなく、文章構造そのものの特徴によって見抜かれています。
AIが作る文章は正確で整っていますが、その整いすぎた構造こそが“違和感”として伝わるのです。
「正しいのに、なぜ伝わらないのか」
AI生成のESは、論理的で誤字もなく、形式的には完璧です。
しかし面接官が感じるのは「正しさ」ではなく、**“温度のなさ”**です。
それは文法や語彙の問題ではなく、「人間の思考の跡」が欠けていることが原因です。
採用担当はESを単なる情報の羅列として読むのではなく、
「この学生は、どう考え、どんな順序で判断したのか」
を見ています。
AIが出力する文章は、こうした“思考の軌跡”が存在しません。
そのため、一見ロジカルでありながら「なぜそう考えたのか」が曖昧で、心に残らないのです。
人事が違和感を覚える“3つの特徴”
ナイテックが複数の採用担当者にヒアリングを行った結果、
AIで作成されたESには、次の3つの共通点があることがわかりました。
① 因果が浅い(Whyの欠如)
AIは「何をしたか」は書けますが、「なぜそうしたか」という背景の文脈を生み出せません。
そのため、文章は常に“行動の説明”で止まってしまいます。
たとえば、
「売上を伸ばすためにSNS運用を行いました。」
という一文。
一見問題はありませんが、採用担当が本当に知りたいのは、
「なぜSNSを選んだのか」
「他の手段と比較してどう判断したのか」
という“意思決定のプロセス”です。
この「Whyの空白」がある限り、どれだけ整った文章でも“薄く”見えてしまいます。
② 文末表現の均一化(〜しました/〜と考えます)
AIが作成したESは、語尾が均一になりがちです。
「〜しました」「〜と考えます」「〜に取り組みました」と同じ調子が続くと、
読んでいる側には“テンプレート的な違和感”が生まれます。
人間の文章には、無意識のリズムや抑揚、文末の変化があります。
一方でAIは、平均的なパターンを出力するため、文章全体が平坦になり、
どれだけ内容が優れていても印象に残りません。
③ 感情の揺らぎがない(人間らしさゼロ)
AIは感情を“再現”することができません。
そのため、文章には「悔しかった」「焦った」「嬉しかった」といった感情の粒が存在しません。
採用担当は、この“感情の揺らぎ”を重要な評価要素としています。
感情の動きは、挑戦や失敗、成長といった経験の証拠であり、
それがない文章は、どこまで行っても「模範解答」に留まってしまうのです。
“整いすぎた文章”は、むしろマイナスに働く
採用担当はESを「情報」ではなく、**“行動の証拠”**として読みます。
多少の誤字や言い回しの粗さがあっても、
そこに思考の跡や現場感があれば、「自分の言葉で書いている」と判断されます。
逆に、完璧すぎる構文や均一なリズムの文章は、
「本人が書いていないのでは?」
「この文章にリアリティがない」
と見抜かれてしまうのです。
AIで作成したESが通らない理由は、AIが悪いのではありません。
“整いすぎた構造”が、結果的に人間らしさを奪ってしまうからです。
次章では、AIで作られたESがなぜ評価されにくいのか。
そして、採用担当がどのようにその“違和感”を判断しているのかを、
実際の面接プロセスと照らし合わせながら解説します。
第2章|AI感のあるESが評価されない“3つの理由”
AIで作られたESは、一見整っていても評価が上がりにくい――。
その理由は単純ではありません。
採用担当が「AIっぽい」と感じた瞬間に、
**「この学生は自分で考えていないのでは?」**という疑念が生まれるからです。
ESは、単なる文章審査ではなく、**面接の“前哨戦”**です。
ここで「再現性のある思考」を感じさせられない学生は、
面接で必ず“整合性の壁”にぶつかります。
AI感のあるESが評価されない理由は、大きく3つあります。
① 面接との整合性が取れない(AI文体は再現不可能)
AIが作成したESは、見た目こそ整っていますが、再現性がありません。
面接では、ESに書かれた内容をもとに質問されます。
しかし、AIに任せきりで書いた学生は、いざ掘られた瞬間に説明が止まります。
たとえばESで、
「課題を特定し、改善策を実行しました。」
と書いていた場合、面接官は必ずこう聞きます。
「その課題はどのように発見したのですか?」
「具体的にどんなプロセスで改善策を決めたのですか?」
AIの文章は、因果が浅いためここで破綻します。
“説明できない文章”は、採用担当にとって最も危険なシグナルです。
なぜなら、「本人の思考が再現できない=入社後に再現性がない」と判断されるからです。
② 熱量が均一で、印象に残らない
AIで生成された文章は、どこを読んでも温度が一定です。
冷静で理路整然としているように見えますが、
面接官が求めているのは「正確さ」ではなく「印象に残る思考の軌跡」です。
「なぜそれをやりたいのか」
「どんな想いで取り組んだのか」
このような“内面の熱量”は、言葉の選び方や間の取り方に表れます。
AIはこの「感情の濃淡」を表現できず、
すべての文章が同じテンションで流れてしまうため、記憶に残りません。
採用担当は、ESを“データ”ではなく“物語”として読んでいます。
だからこそ、表面的な綺麗さよりも、心の振れ幅を伴う文章の方が評価されやすいのです。
③ 「自分で考えていない」=再現性のない学生と判断される
採用活動において、最も重要視されるキーワードが「再現性」です。
つまり、「この学生は入社後も同じ思考プロセスで成果を出せるか」。
AI任せで作ったESには、**「考えた証拠」**がありません。
そのため、たとえ内容が正しくても、採用担当はこう感じます。
「この学生は、誰かに整えてもらえば良い文章は書けるが、自分では考えられないかもしれない。」
企業が欲しいのは、文章が上手い学生ではなく、思考の再現性がある人材です。
ESでそれを見せるためには、論理の正確さではなく、
**「自分の頭で考えた跡」**を残すことが重要なのです。
「ESの一文を掘られた瞬間」にバレる構造
実際の面接では、ESの一文をもとに掘り下げ質問が行われます。
ここで回答が浅いと、すぐにAI任せだったことが露呈します。
採用担当は文章を“情報”として読むのではなく、“行動証拠”として読み解いています。
そのため、どんなに綺麗な文章でも、行動の背景が曖昧なESは高く評価されません。
AIを使ってESを書くこと自体は問題ではありません。
しかし、**AI任せにしたESは、思考の再現性がない“空洞の構造”**になってしまうのです。
次章では、ChatGPTを“敵”ではなく“思考補助輪”として活用し、
「人事に伝わるES」を作るための正しい使い方を解説します。
第3章|ChatGPTを正しく使えば“通過率が上がる”
AIで書いたESが評価されない理由は、「思考をAIに委ねた」ことにあります。
しかし逆に言えば、AIを“使う”のではなく“使いこなす”学生は、
思考の深さと整理力を両立できる希少な存在として評価されます。
採用担当の中にはこう語る人もいます。
「AIを上手く活用している学生は、構成が明確で思考の筋が通っている」
つまりAIを“補助輪”として使えば、通過率を上げることは十分に可能なのです。
ChatGPTの本質は「生成」ではなく「思考の可視化」
多くの学生が誤解しているのは、ChatGPTを“代筆ツール”として使うことです。
しかし本来の価値は、自分の思考を構造化してくれる“思考鏡”としての機能にあります。
人間が得意なのは「経験」や「感情」ですが、
AIが得意なのは「情報整理」や「論理検証」です。
この両者を分業することで、ESの完成度は一気に上がります。
たとえば、ChatGPTに「このエピソードを基に構成案を作って」と指示すれば、
因果構造(現状→課題→打ち手→結果)を自動で整理してくれます。
その上で、自分の実体験を肉付けし、感情や背景を加えれば、
“人間×AI”のハイブリッドESが完成します。
ChatGPTを活用する3ステップ
ナイテックでは、通過率の高い学生が共通して行っている
「AI活用3ステップ」を以下のように整理しています。
① ChatGPTに「構成案(章立て)」を作らせる
最初から文章を書かせるのではなく、まず**構成(骨組み)**を作らせます。
例:「このガクチカを基に、志望動機に繋がる構成案を3つ出してください。」
ChatGPTは膨大な文章データをもとに、一般的な論理展開を提示してくれます。
ここでの目的は「正解を得ること」ではなく、
“自分の考えをどの位置に置くか”を知ることです。
② 自分の原体験を流し込む
構成ができたら、次は自分の経験と言葉を入れます。
この段階では、「AIっぽさ」を恐れず、むしろ感情を積極的に入れるのがポイントです。
たとえば、
「焦り」「悔しさ」「意地」などの言葉を敢えて使う。
それが文章に“生身の体温”を与えます。
AIが作った論理に、人間が「物語」を吹き込む。
この二重構造こそが、最も再現性が高く評価されやすいESの形です。
③ ChatGPTに「一貫性・論理の検証」を依頼する
最後に、完成した文章をChatGPTに再度読み込ませ、
「この文章の一貫性と採用担当視点での違和感を指摘してください。」
と依頼します。
AIは感情を理解できませんが、「構造の歪み」は正確に検出します。
自己分析・志望動機・ガクチカの流れに矛盾がないかを確認するには、最適な相棒です。
“考えるためのAI”が、思考を鍛える
AIを使ってESを書くことは、決してズルではありません。
むしろAIを通して自分の思考を客観視できる学生は、
面接での受け答えも論理的で一貫しています。
ChatGPTは「文章を作るツール」ではなく、**「自分の思考を映す鏡」**です。
AIを利用して考える過程を磨くことで、
“再現性のある思考力”が自然と身につくのです。
次章では、実際に人事が評価する「AIでも通過するES」の共通点を紹介します。
AIの支援を受けながらも、“人間の意思”が伝わるESとはどのようなものなのか。
採用担当の視点から、具体的に解説していきます。
第4章|人事が“AIでも評価するES”の共通点
ここまでで触れたように、ChatGPTで作ったESが落ちる原因は、
AIの使用そのものではなく、思考をAIに丸投げしてしまうことにあります。
一方で、採用担当の間ではこうした声も増えています。
「AIを使っていても、自分の言葉で考え抜かれたESはわかる」
「構成が整っているだけでなく、決断の根拠まで語れている学生はむしろ印象がいい」
つまり、人事が評価するのは**“構造”ではなく“意図の精度”**です。
ChatGPTを使いながらも通過するESには、明確な共通点があります。
① 経験と価値観が因果でつながっている
AIの文章は「出来事の説明」で終わりがちです。
一方で、評価されるESは「経験 → 学び → 価値観」まで一気通貫で繋がっています。
たとえば、
「アルバイトでリーダーを任された」ではなく、
「チームの課題を見極め、メンバーが自走できる仕組みを整えた」
というように、“経験の中で何を重視して行動したのか”が明確です。
そしてその行動を通じて形成された価値観が、志望動機やキャリア軸に接続している。
この一貫線が通っているESは、AIの整った文章よりも、
はるかに“人間らしい説得力”を持ちます。
② 決断の背景が語られている
採用担当は、結果そのものよりも、“選択の理由”を評価します。
だからこそ、AI的な「事実列挙」ではなく、
「なぜその方法を選んだのか」「他の案はなぜ捨てたのか」という思考の分岐点を見たいのです。
たとえば、
「SNS運用でフォロワーを増やしました」ではなく、
「チームの強みが“顧客対応力”だと考え、それを可視化するためにSNSを選びました」
という一文のほうが評価されます。
結果よりも、“選択の根拠”に個性が出る。
そこに、AIでは再現できない人間の判断軸が存在します。
③ 企業との接点が“仮説”で語られている
多くの学生が「御社の理念に共感しました」と書きますが、
採用担当が見ているのは共感そのものではなく、**“理解の深度”**です。
AIが作る志望動機は、一般論の域を出ません。
しかし評価されるESは、企業理解をもとに仮説を立てています。
たとえば、
「御社は“暮らしを支える”というビジョンのもと、◯◯事業で△△に挑戦しています。
その中で、私の□□の経験は××の部分で活かせると考えています。」
このように、企業の提供価値と自分の経験を仮説的に結びつける構造がある。
完璧な答えでなくても、「自分なりに考えている」姿勢が伝われば、それが評価されるのです。
“AIで補強し、人間で意味づける”
採用担当がESを評価する際、文章の整合性よりも、
「この学生は、自分の経験から何を学び、それをどう活かそうとしているか」
を最も重視しています。
AIで整理された構造は、理解を助けるための“骨格”にすぎません。
そこに自分の言葉で意味を与え、背景や感情を添えることで、
ようやく“血の通ったES”になります。
ChatGPTで通過する学生の共通点は、
AIに思考を奪われるのではなく、AIを通して自分の思考を深めている点にあります。
次章では、実際に使えるChatGPTプロンプト例を紹介します。
「どう聞けば“人事目線で整ったES”が作れるのか」
という実践的なステップを具体的に解説します。
第5章|ChatGPTでESを仕上げるための“プロンプト例”
ここまでで解説してきた通り、ChatGPTは「文章を代わりに書くツール」ではありません。
最も価値を発揮するのは、自分の思考を整え、論理を検証する“壁打ち相手”として使うことです。
AIをうまく使いこなす学生は、必ず「質問の仕方(プロンプト)」を工夫しています。
つまり、ChatGPTへの問いの精度が、そのままESの質に直結するのです。
以下では、人事目線で見ても“自然で再現性の高いES”を作るための、
具体的なプロンプトを5つ紹介します。
① 構成を設計するためのプロンプト
ChatGPTの最大の強みは、「文章構造を瞬時に整理できること」です。
最初に“型”を作ることで、後の修正工数が大幅に減ります。
プロンプト例:
「以下の経験をもとに、志望動機に繋がる構成案を3パターン作成してください。
現状→課題→行動→結果→学びの流れを意識して、因果関係が明確な章立てにしてください。」
ChatGPTはこの指示で、複数のストーリー構成を提示します。
その中から“自分の納得できる流れ”を選ぶことが、第一の思考訓練です。
② 一貫性を検証するためのプロンプト
ESの多くは、志望動機・自己PR・ガクチカの一貫性が欠けています。
ChatGPTを使えば、自分の思考軸がズレていないかを客観的にチェックできます。
プロンプト例:
「以下の文章を読み、採用担当の視点から見た一貫性の欠如・論理の弱点を3つ指摘してください。
また、その改善提案も併せて出してください。」
この指示により、AIが“構造の歪み”を正確に洗い出してくれます。
自分では気づきにくい矛盾を指摘されることで、ES全体の精度が格段に上がります。
③ 企業との接点を可視化するためのプロンプト
「なぜその企業なのか」を明確に語れない学生が多い中で、
ChatGPTは“提供価値と自分の価値観の共通点”を構造化するのに最適です。
プロンプト例:
「企業の提供価値(ミッション・事業内容)と、私の経験の共通点を因果構造で整理してください。
また、その共通点を志望動機に自然に繋げる1文を提案してください。」
この質問によって、「共感」から「論理的接続」へと内容を昇華できます。
採用担当に伝わる志望動機は、**“好きだから”ではなく“構造が噛み合っている”**ものです。
④ 行動のリアリティを補強するプロンプト
AIが作る文章の弱点は“行動の手触り”がないこと。
その補完にも、ChatGPTを活用できます。
プロンプト例:
「このエピソードの行動部分を、より具体的にイメージできるように修正してください。
誰と、どこで、何を、どのように、の5W1Hを必ず明示してください。」
この指示を与えることで、ESの抽象度が下がり、面接でも一貫して話せる内容に整います。
⑤ 面接を想定した“掘り下げ想定”プロンプト
ESは書いて終わりではなく、面接で“掘られる”ことを前提に設計すべきです。
ChatGPTに質問役を任せることで、実践的な想定問答を作ることができます。
プロンプト例:
「以下のESをもとに、採用担当が深掘りしそうな質問を10個出してください。
また、それぞれに対して理想的な回答例も併せて作成してください。」
AIが提示する質問は、実際の面接で出るものと驚くほど近いです。
この工程を繰り返すことで、**“どこを掘られても破綻しないES”**が完成します。
“生成”ではなく“検証”として使うのが正解
ChatGPTを活用する本当の意味は、**「自分の思考の型を磨くこと」**にあります。
AIに任せるのではなく、AIを通して“自分が考えていない部分”を見つける。
この使い方ができる学生は、ESの完成度だけでなく、面接でも安定感が増します。
採用担当は、文章の出来栄えよりも、
「この学生は、どれだけ考え抜いてこの答えにたどり着いたのか」
を評価します。
ChatGPTは、その“考え抜くプロセス”を鍛えるための最高のツールです。
第6章|AIで“思考を磨き”、人間で“熱量を加える”
ChatGPTでESを書くことは「ズル」ではありません。
それは、就活という“思考のトレーニング”を効率化する、新しいリテラシーです。
AIを使うことに後ろめたさを感じる学生もいますが、
採用担当が見ているのは「使ったかどうか」ではなく、
「その結果、自分の思考がどれだけ磨かれたか」
という一点です。
AI任せのESは、再現性がない
AIが生み出す文章は、正確で、整っていて、そして“薄い”。
なぜなら、そこに「選択の跡」「葛藤の痕跡」が存在しないからです。
一方で、AIを使いこなす学生は、自分の考えを客観視しながら、
どの要素を残すか・削るかを自分で決めています。
この「取捨選択の痕跡」こそが、採用担当が“人間らしさ”として感じ取る部分です。
ChatGPTは「書くツール」ではなく「思考の鏡」
ChatGPTは、思考を置き換える存在ではなく、
**自分の頭の中を可視化してくれる“鏡”**です。
AIに問いを投げることで、自分の考えの抜けや矛盾が見えてくる。
そして、そのズレを修正しながら精度を高めていく。
このプロセスを繰り返すことで、文章力よりも思考力そのものが鍛えられます。
就活は、情報戦ではなく「思考戦」です。
ChatGPTは、あなたの考える力を底上げしてくれる最強のトレーナーなのです。
“整った言葉”ではなく“選ばれた言葉”を
ESで本当に伝わるのは、整った文章ではありません。
面接官が心を動かされるのは、**“選ばれた一文”**です。
「悔しかった」「怖かった」「それでも挑戦した」
このような等身大の言葉が、読み手に“生身の温度”を届けます。
ChatGPTで構造を整え、人間の言葉で熱を加える。
その掛け算こそが、AI時代の“通るES”の新しい形です。
採用担当が最後に見るのは「意思」
採用担当は、文章の上手さよりも、
「この学生は、自分の意思で考え、動いてきたか」
を見ています。
AIで整えた構造に、自分の意思を通わせる。
その一点を意識するだけで、ESは確実に変わります。
AIは“骨格”を整え、人間が“血を流す”。
だからこそ、AIを上手く使う人ほど、人間らしいESを書けるのです。
ES~面接対策まで徹底した個別指導ならナイテック
ChatGPTを使いこなす学生が、なぜ通過率を上げているのか?
答えは、“AIで整え、人間で意味づける”ことにあります。
ナイテックでは、AIの使い方だけでなく、
人事が「伝わる」と感じる言葉選びまでを徹底的に指導。
あなたのESを「整っている」から「惹きつける」へ。
👉 AI時代に通用するESを、一緒に作りませんか?